昭和16年(1941年)11月19日
野村・来栖両大使、ハル米国務長官と会談、野村・来栖は独自の打開策を提案
|
|
 |
資料1:B02030722600 14 昭和16年11月18日から昭和16年11月19日(7画像〜17画像右)
「昭和16年11月18日野村大使発東郷外務大臣宛公電第一一三一号(極祕、館長符号)(写)」
|
 |
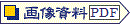 |
 |
資料2:B02030722600 14 昭和16年11月18日から昭和16年11月19日(22画像〜25画像右)
「昭和16年11月18日野村大使発東郷外務大臣宛公電第一一三四号(極祕、館長符号)(写)」
「昭和16年11月18日野村大使発東郷外務大臣宛公電第一一三四号ノ二(続)(極祕、館長符号)(写)」
|
 |
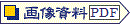 |
|
|
昭和16年(1941年)11月19日、午前0時半より午前3時15分(米時間18日午前10時半より午後1時15分)にかけて、野村駐アメリカ大使と来栖特命大使はハル米国務長官と会談を行ない、その中で交渉方針についての独自の提案を行ないました。
資料1は、東郷外務大臣に対して電送された会談の報告の写しです。これによれば、野村はハルとの議論の中で、三国同盟と諸軍事政策をめぐる日米の見解の相違について「斯カル根本的問題ハ限ラレタル時間内ニ解決スルコトハ困難ナリ然ルニ南西太平洋ノ情勢ハ極メテ緊迫シ居レリ」と考え、ハルに対してひとつの独自の提案を切り出しています(4画像目の末尾あたりより)。この提案とは、「差当リ斯カル緊張ヲ緩和スルコト」を目的とし、「凍結令実施前ノ事態ニ復帰スルコト」、すなわち、日本は南部仏領インドシナより撤兵し、アメリカは日本に対する資産凍結を解除するということによって、南方における日米双方の軍事力強化の必要をなくした上で交渉を進めることにしたい、というものでした。この提案に対してハルは難色を示しましたが、野村・来栖両大使が説得しようと試みた結果、「日本政府ノ首脳カ日本ハ何処迄モ平和政策ヲ遂行スルモノナルコトヲ明カニスルナラハ自分ハ英国、和蘭等ヲ説キ凍結令実施前ノ状態ニ復帰スルコトヲ考慮シ差支ナシ」との返答を受けたとあります。ハルは続けて、以上のような措置を受けた日本政府が「益々平和ノ傾向ニ向フ様ニナルコト」が重要であると付け加えています。これに続いて、議論は日本と重慶国民政府との和平問題、通商問題、戦後を見越した各地における日本の駐兵の問題へと移っています。
資料2は、上記の報告に続いて野村より東郷に送られた電報です。ここで野村は、資産凍結令以前の状態への復帰、日本軍の南部仏領インドシナよりの撤退、という自身の提案について再度説明をしてから、この提案に対するハルの返答内容を受け、従来は中国における日本の駐兵問題を重視していたアメリカが、次第に三国同盟をめぐる日本の平和政策に議論の重点を移してきていることを強調しています。ここから野村は、この状況においては「乙案」に対してアメリカの同意を得ることは「甲案」よりもさらに困難であろうことを指摘し、さしあたって「乙案」の中の資産凍結解除と「物資獲得」(日本に対する物資供給)という点に主眼をおいた妥協を出発点として他の諸問題の解決を目指すべきではないか、という提案を改めて東郷に対して行なっています。
|
 |